こんにちは、トリマーの瀬奈です。
今回学んだのは「主な検体検査の手順」について、ブログにまとめました。動物病院や出張トリミング先で役立つ知識もたくさんあったので、復習を兼ねて書いていきます✍️
🐶 検体検査ってなに?
検体検査とは、血液・尿・便など「身体の一部を取り出して行う検査」のことです。
動物の健康状態や病気の有無、治療の経過を見るためにとても大切な検査です。
🩸 血液検査の基本とポイント
🔍 検査の種類と使う検体
| 検査の種類 | 使用する検体 | 主な検査項目 |
|---|---|---|
| 血球計算検査 | 全血(EDTA塩) | 赤血球・白血球・血小板など |
| 生化学検査 | 血漿または血清(ヘパリン) | 肝臓や腎臓、電解質など |
| ホルモン検査 | 血漿または血清(例外あり) | 甲状腺ホルモン・副腎ホルモンなど |
👉 ポイント:検査項目によって抗凝固剤(紫・緑・黒のキャップ)を使い分けるのが重要です!
💉 採血の注意点
- 採血前は12時間絶食が理想(特に生化学検査)
- 太めの血管から採血、できるだけ細い針は避ける
- 採血部位の消毒はしっかり乾かす
- 採取後は抗凝固剤の種類によって順番に分注
🧪 尿検査:採り方で結果が変わる!
採尿方法の比較
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自然排尿 | 侵襲性がない | 雑菌が混入しやすい |
| 圧迫排尿 | 採りやすい | 膀胱逆流や破裂のリスクあり |
| カテーテル | 比較的清潔な尿が得られる | 尿道損傷や感染のリスク |
| 膀胱穿刺 | 最も清潔な尿が得られる | 技術が必要でリスクもある |
👉 検査は採尿後30分以内が理想!
保存するなら冷蔵で4時間以内、冷凍はNG!
💩 糞便検査:寄生虫や消化状態をチェック
- 自然排便か、直腸便の採取が基本
- 検査は新鮮便を使うのが鉄則! すぐに検査できない場合は乾燥を防いで冷蔵保存
- 検査内容:
- 顕微鏡で寄生虫卵や結晶の確認
- 消化能のチェックにはルゴール液やズダンⅢ染色を使用
🧬 その他の検査について
🧫 病理検査
- 細胞診(塗抹・染色)や組織検査では標本の作り方・固定・保存が超重要!
- ホルマリン固定では10倍量の緩衝液に浸すことが基本
🦠 微生物検査
- グラム染色やKOH法などで病原体を直接観察
- 培養検査は抗生剤投与前に!
🧬 遺伝子検査
- 感染症の特定や遺伝性疾患の診断に
- スワブや血液、糞便など様々な検体を使用
📝 最後に:精度の高い検査のために
最後に特に強調されていたのがこちらの3つ:
✅ 検査精度を高める3本柱
- 適切な検体の採取
- 適切な保存
- 適切な検査手技
病院全体でルールを統一することが、安全で正確な診断につながるというお話でした。
💡 感想と学び
検査って獣医師だけが関わるものじゃなくて、看護師やトリマーが補助に入ることも多いんですよね。
検体の扱いを間違えると、せっかくの努力も無駄になってしまうので、今回学んだことを今後に活かしていきたいと思いました✨
🛒 関連アイテム紹介(PR)
以下のアイテムは動物病院やトリマー業にも使えるものです🧼💉
リンク
リンク
リンク
※上記はアフィリエイトリンクを使用しています。気になる方はぜひチェックしてみてください。

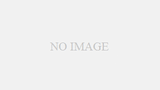
コメント